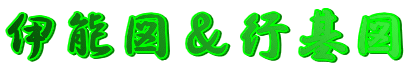
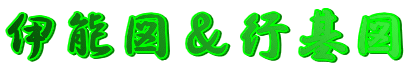
2002年度は、2学期から6年の担任になりました。
社会科は、伊能忠敬から授業をすることになっていました。
でも9月は夏休みのあとで、子どもたちに何とか集中してもらえる工夫が必要でした。
私は、日本古代史は大好きですが、中世、近世は得意ではありません。
ということで、授業にあきられないようにと教材研究をしました。
○AとBの地図を見て気がついたことを書きなさい。
| A の 地 図 (行基図) | B の 地 図 (伊能図) | |
| 児童の解答例 | ・山城国が中心 ・陸奥がおおざっぱ ・北海道がない |
・伊能忠敬が書いた地図かな。 ・今の日本の地図かな。 |
| 備 考 | 【行基図を拡大した物を提示】 行基(668〜749)が作ったと伝えられている。 畿内を中心にし、律令制の街道=七道が示されている。かなりおおざっぱに国々が描かれている。「拾芥抄」(14世紀成立刊6冊鷹見家歴史資料) |
【授業では伊能図を略したものを提示】 第一測量1800年。1818年に亡くなるまで「大日本沿海與地全図」の作成を続ける。 現在の地図とあまり違わない。 |
○AとBの地図は、いつごろ作られたと思いますか。
<Aの地図>
・奈良(山城国)を中心とした時代から江戸初期まで使用されたという。
< Bの地図>
・江戸時代後半
※ここでAが行基図であること、Bが伊能図あることを知らせた。
<補助発問…どうしてAの地図は、長い間進歩しなかったのか?>
(児童の解答例)
・日本国内だけの移動距離の限られた地域だからかな
・鎖国の影響もあるだろう。外国からの危機感が少ない。
○(伊能図と今の地図を重ねた資料を提示し)現在の地図と比べて気がつくことを発表して下さい。
(児童の解答例)
・ほとんど今の地図と変わらない。
・すごい正確。
◎この後の児童の調べるテーマ例
・伊能忠敬は、どのようにしてこんなに正確な地図を書いたか。