電話でのご予約・お問い合わせはTEL.03-3760-9555
〒153-0061 東京都目黒区中目黒5-28-17
ブライト動物病院
Bright Veterinary Hospital
予防医療preventive medicine
近年、人の動物に対する考え方が変わってきており、ペットから人生のコンパニオン(伴侶)やファミリー(家族)であるといった関係に変わってきました。これらの愛すべき動物を少なくとも予防できる病気で死にいたることがないようにしていきましょう。
ワンちゃんが行わなくてはならない予防としては、混合ワクチン、狂犬病予防ワクチン、フィラリア症予防、ノミダニの予防が挙げられます。
ねこちゃんが行わなくてはならない予防としては、混合ワクチン、ノミダニの予防があります。
混合ワクチンは以下にあげたウイルス病を予防するワクチンで、非常に重要な予防です。中には死にいたる病気もありますので必ず接種するようにしてください。
ワクチネーションは仔犬時で2〜3回の追加接種を行い、成犬でも年1回の追加接種が必要です。現在では3種から10種の混合ワクチンがあり、犬の行動範囲や環境、体質により選択します。詳しくは診察時にご相談ください。
発熱、下痢、神経症状などが起こり、死亡率も高い病気です。治ってもいろいろな後遺症が発現する事があります。
犬パルボウイルス感染症
血液が混じった下痢や嘔吐を起こし、伝染性が強く死亡率も高い病気です。また仔犬では突然死を起こすこともあります。
犬アデノウイルス2型感染症
肺炎や扁桃炎などの呼吸器病を起こす伝染病です。
犬伝染性肝炎
肝炎を主とした嘔吐や下痢、食欲不振などが起こり、眼が白く濁ることもあります。仔犬では突然死することもあります。
犬パラインフルエンザ
咳や鼻水、扁桃腺炎などの呼吸器症状を呈します。他の細菌やウイルスと混合感染を起こし症状が悪化します。(ケンネルコフ)
犬レプトスピラ病(黄疸出血型、カニコーラ型)
人畜共通感染症で、細菌によって腎臓や肝臓がおかされる病気です。いろいろなタイプがあり、代表的なのは歯ぐきの出血や黄疸が見られる黄疸出血型と、高熱、嘔吐、下痢を起こすカニコーラ型があります。
犬コロナウイルス感染症
下痢や嘔吐などの症状が見られる感染症で、パルボウイルスとの混合感染では死にいたることもあります。
猫の混合ワクチンについて
現在、猫のウイルス病については完全なる治療法がありません。またこれらの病気には感染すると命にかかわるものもあります。 したがって、これらの病気については予防することが最善の治療といえるでしょう。
猫のワクチンには3種から5種混合ワクチンがあります。何種を接種するかについては、その猫ちゃんの環境状態によって変わりますので、かかりつけの獣医師に相談ください。
猫に対するワクチネーションは、子猫の場合は生後2〜3ヶ月の時期に1回目を接種、その後2〜4週間後に2回目の接種を行います。 成猫の場合は年1回追加接種を行います。
ワクチンによって得られた免疫は一生続くものではありませんので、継続してワクチン接種をするようにしてください。
ワクチンで防げる病気には次のようなものがあります。
猫ウイルス性鼻気管炎
猫ヘルペスウイルスによって起こる伝染病で、感染猫のくしゃみや分泌物などからうつります。食欲がなくなり、発熱と激しいくしゃみや咳を示し、多量の鼻水や目やにがでます。別名「猫かぜ」ともよばれ、伝染性が強く、他のウイルスや細菌との混合感染により激しい症状となり、子猫では死亡することもあります。
猫汎白血球減少症
原因菌は猫パルボウイルスで、感染経路は感染猫との接触、感染猫の糞、尿、嘔吐物などの接触でも感染します。高熱、嘔吐、下痢などの症状を示し、血液の白血球の数が著しく減少します。脱水症状が続くと猫は衰弱し、特に子猫では死亡率の高い病気です。
猫白血病ウイルス感染症
オンコウイルス(レトロウイルスの1種)によって起こる伝染病で、猫同士の毛づくろいなどを通じて口や鼻から伝染します。リンパ肉腫や白血病などの腫瘍性疾患を始め貧血、汎白血球減少などの骨髄機能低下、腎炎あるいは免疫不全による感染症を起こします。これらの症状に対する根本的な治療法はなく、死亡する危険性の高い疾患です。
猫カリシウイルス感染症
猫のカリシウイルスによる伝染病で、感染猫との接触で伝播しますが、くしゃみによる飛まつ感染や、手、衣服、食器などによる間接的な接触でも伝播します。
クラミジア感染症
クラミジアによる感染症で、感染猫との接触により感染します。症状は粘着性の目ヤニを伴う慢性持続性の結膜炎です。また、くしゃみや鼻水、咳なども見られ、気管支炎や肺炎に移行する場合があります。
狂犬病ワクチンは狂犬病予防法により、すべての犬に接種が義務づけられています。生後91日以上の犬は飼いはじめてから30日以内に1回、その後は毎年1回の接種を受けなければなりません。またワクチン接種により交付された注射済票を必ず犬につけておかなければなりません。
フィラリア症は蚊によってうつる伝染病で、心臓にそうめん状の虫が寄生し、咳、呼吸困難、吐血、腹水などの症状が見られ、治療しなければ死にいたる病気です。
感染した場合には、外科的に寄生虫を摘出する手術や長期の内科的治療が選択されますので、予防により感染を防ぐことが重要になります。
今はいい薬があり、一ヶ月に一回お薬を飲ますことで予防できます。毎年、5月から12月まで飲ませてください。
その年、初めての投薬前には血液検査が必要です。フィラリアに感染しているワンちゃんに予防薬を飲ませると、ショック症状を呈することがありますので注意してください。
都内は動物密集地域のためノミも多く、夏場などは1回散歩に行くだけでも1〜2匹のノミの感染を受けるでしょう。ノミの感染を受けるとアレルギーを起こし皮膚病になったり、お腹に虫が寄生(条虫症:サナダムシ)することがあります。
ノミの寄生は春から秋にかけて多くみられますが、冬場でも見られますので、1年を通して予防することをお勧めします。
ノミの予防法については獣医師にお尋ねください。
![]()
健康診断について
人医療では「予防に勝る医療なし」と言われ、早期発見、早期治療が重要視させています。動物医療でも同様で、特に言葉が話せない動物たちの病気を早期に発見して、苦痛や不安を減らし、生活習慣の改善や体調管理をしてあげましょう。また、ワンちゃんネコちゃんは生後1年(大型犬は2年)で人間でいう20歳になり、その後1年で4〜5歳年を取ります。したがって人間よりも5〜6倍早くで年を取ります。
年齢6歳までは年1回、6歳以上は年2回の健康診断が推奨されます。
簡易検査
外来診察による検査になります。
身体検査: 問診 視診 触診 聴診 カウンセリング
血液検査: CBC検査(貧血や脱水 感染症の有無などがわかります)
血液生化学検査10項目(肝臓 腎臓などか各臓器の状態やおおまかな全身状態がわか
ります)
糞便検査: 腸管内の寄生虫や感染症の有無、消化管の機能がわかります
尿検査 : 腎臓機能 膀胱炎、尿石症の有無などがわかります。
ペットドック
日中預かりによる検査になります。
身体検査 : 問診 視診 触診 聴診 カウンセリング
血液検査 : CBC検査(貧血や脱水 感染症の有無などがわかります)
血液生化学検査13項目(肝臓 腎臓などか各臓器の状態やおおまかな全身状態
がわかります)
糞便検査 : 腸管内の寄生虫や感染症の有無、消化管の機能がわかります
尿検査 : 腎臓機能 膀胱炎、尿石症の有無などがわかります。
レントゲン検査: 胸部は心臓、肺、気管などの形態的な異常がわかります。
腹部は肝臓、腎臓、脾臓、膀胱等各内臓の形態的な異常および脊髄、股関節など
の状態がわかります
腹部超音波検査: 肝臓、腎臓、脾臓、副腎、膀胱、前立腺、子宮、消化管、腹腔内リンパ節の超音
波による画像診断
心臓検査
日中預かりによる検査になります。
心臓超音波検査:弁膜症の有無、心筋の状態や心臓の機能がわかります。
心電図検査 :心臓の動きを電気的な波形にして調べます。
ホルモン検査
甲状腺、副腎の機能検査
甲状腺機能亢進症は高齢のネコちゃんの5頭に1頭はかかると言われております。
副腎皮質機能亢進症はワンちゃんで多飲多尿多食の症状が見られます。
アレルギー検査
アレルギーの有無やアレルギー物質について調べます。
ペットドックの注意事項
・ペットドックは予約制になっております。お電話にてご予約ください。
・前日の夜12時から絶食絶水での来院をお願いいたします。
・検査当日は午前9時〜11時に来院していただき、午後4時以降のお迎えになります。
・便はなるべく新鮮なものをラップ、ビニールにくるみご持参ください。
・尿検査を行いますので、できるだけ朝は排尿させずにご来院ください。または後日お持ちいただいて もかまいません。
![]()
無麻酔歯石除去について
ワンちゃんネコちゃんの歯石除去は、全身状態を確認後、麻酔をかけて行うのが一般的です。なぜなら、ワンちゃんネコちゃんはおとなしく我慢して口をあけていてくれないからです。時間をかけて正確に行うことで、歯の裏側や歯周ポケットなどの汚れや歯石を確実に除去し、また安全に行うことができるのです。また表面の目立つ歯石を取ってしまう事で細部を見逃してしまい、結果的に悪化することもあります。「日本小動物歯科研究会」「アメリカ獣医歯科学会」も無麻酔歯石除去については否定的な見解を発表しております。
日本小動物歯科研究会の見解: http://sa-dentalsociety.com/news/dental%20scaling.pdf
しかし、歯が悪くうまくご飯が食べられないにもかかわらず、高齢、心臓が悪いなどの理由から麻酔をかけられず、歯周疾患については放置されているケースも見られます。
無麻酔による歯石除去はメリットとデメリットがあり、当病院で行うべきかどうか非常に判断に苦しむ問題であると思われます。
当病院では歯周病の程度と麻酔に対するリスクを考慮したうえで、ワンちゃんネコちゃんが性格的に問題ないと判断した場合に限り、無麻酔による歯石除去を行います。
無麻酔歯石除去をご希望の方は診察時にお尋ねください。
Bright Animal Hospitalブライト動物病院
〒153-0061
東京都目黒区中目黒5-28-17
TEL 03-3760-9555

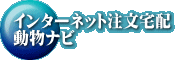
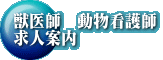
お役立ちリンク集
公益社団法人 日本獣医師会
公益社団法人 東京都獣医師会
目黒区 犬の登録 狂犬病注射
夜間救急動物病院ー目黒
動物取扱業登録書
ブライト動物病院
東京都目黒区中目黒5-28-17
保管 13東京都保第003968
登録 平成25年5月15日
有効期間 平成30年5月14日
動物取扱責任者 江藤朋子