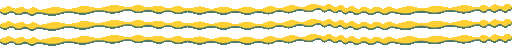
日光社寺の修復コース
コーディネーター1(Harabird)
世界文化遺産
7月2日に日光の社寺を修復している方に、日本が世界に誇る日光東照宮の彫刻の修復の仕方を学びました。
「修復」は、とても時間がかかり神経を集中しなければならない作業です。でも、「修復」に参加した児童は、「修復」を修学旅行の最高の思い出とアンケートに書いてくれました。それは、単に金箔をはるのではなく、そこの携わる方々の情熱と技術に感動したからです。
また私自身も、今回はこの修復の現場に3回足を運びましたが、いつもあたたく迎えて下さった職員の方々に本当に感謝しています。
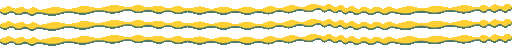
なんと、修復中の「想像の象」を間近に見ることができました。
金箔の輝きと何とも言えない色合い。
修復の技術に感動
| ちょっと、干した魚のようです。今回は、修復の練習ということで膠(にかわ)で教えていただきました。 この膠で、金箔(きんぱく)をはっていきます。 |
|
| 金箔をはっているところ。子供の表情は真剣そのもの。 膠をぬって、そっと金箔を乗せるだけなのですが、手がふるえ思うようにいきません。 |
|
| 半分くらい金箔をはったところです。 ところどころはがれていても、後できちんと直せる技も教わりました。 |
|
| 色もつけ少しだんだんと「修復」気分になっています。ぐんじょうなどの色は、どれも天然の石から作ったものです。 | |
| 花びらも出来てきました。 | |
| 色は、細かくだいた石を水でていねいにねって出します。 | |
| 日光の東照宮に行くと、少し色あせた絵や彫刻を目にします。 でも大丈夫! 日光が、世界文化遺産に指定された理由の1つは、こうした絵や彫刻を完璧に修復できるプロがいるからです。 |
|
 |
これぞ職人芸!!! 上の半分は、修復の名人(プロ)の技。 下の方の金箔は、校長先生が子供たちのために作品を完成しようと必死にはったところです。 |
今回の修復作業
1.ニカワをぬる
2.金箔(きんぱく)をおす
3.ロクショウした色をぬる
4.グンジョウした色をぬる
5.シュドをぬる
6.シュ色をぬる
7.ゴフンでせんがき
8.ロクショウうわ色をぬる
9.グンジョウうわ色をぬる
子供たちの感動
子供たちは、修復の仕方を学んだあと、再び東照宮に自分の小遣いを払って入場しました。12時半だというのに、昼食はとっていません。「後で食べる。」と言うのです。東照宮をあんなに真剣に見て回る子供たちに本当に感動しました。
帰りの特急電車を待つ時間で、「修復」グループの子供たちが、ガイドブックに載っているパン屋さんのパンや駅弁のマス寿司などをおいしく食べる姿が印象的でした。
※今回の食事は、各課題ごとで食べる場所・時間が違います。グループ行動に自信あり。
| 修学旅行前 |
◇メンバーの顔合わせをする。 ◇世界文化遺産としての日光の社寺について考える。 ・文化遺産を守る人々 ・いろいろな彫刻など ◇日光の歴史について学ぶ ◇修復の仕方の概略をつかむ。 ・修復前と後の比較 ・修復に使う道具と材料 ・パソコンを使って、「想像の象」(漆塗りだけの段階の写真)をいろいろな資料から忠実に再現する。 ◇自分の調べたい課題を決める。 |
| 修学旅行 | ◇五重塔周辺見学 ◇修復の作業所で専門家の方の話を聞き、歴史や修復で使う道具や顔料について知る。 ◇金箔や顔料を使って修復体験をする。 ◇東照宮を再度見学し、実際の彫刻や建造物の様子を見学する。 |
| 修学旅行後 | ◇修復作品展示 ◇それぞれが新聞や作文などに修復についてまとめる。 |